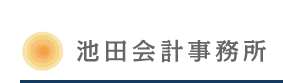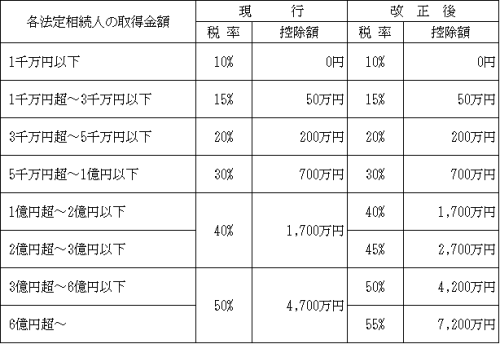「消費税率10%引上げ時の軽減税率について」
こんにちは。
相談役・税理士の池田茂雄です。
今回は、「消費税率10%引上げ時の軽減税率について」述べてみます。
平成29年4月より消費税率が8%から10%に引上げられることが既に決まっている。
この際、生活必需品の税率を低く抑える軽減税率の導入について、これまで対象品目として「酒類を除く飲食料品」・「生鮮食品」・「精米」の3案を軸に検討が進められてきた。
ところが、この度、消費税率を10%に引上げる際の負担軽減策として、財務省が新たな対応策を発表した。それによると、税率が10%に引上げられるにあたり、「酒類を除く飲食料品」(外食を含む)を軽減税率の対象とする。そこで、複数の税率を設けると事業者の経理処理が複雑になるなど問題点が多いため、10%の税率を課した上で、払いすぎた税金分として2%相当額を後から給付する方式である。財務省は、この負担緩和策を「日本型軽減税率制度」と説明している。この場合、当初は所得や世帯構成などに応じて消費額を推計するという方式も示されていたが、これでは実際の買い物とは関係のない金額が給付されることになるとのバラマキ批判があり、そこで今年10月から実施されるマイナンバーカード制度の活用に着目し、現在のところその方向で検討が進められている。小売店に設置した情報端末を使い、買い物の際の金額などのデータをマイナンバーカードのICチップに記録し、その後、カードに記録された情報をもとに2%相当額が受け取れるというものである。
この財務省案だと、商品の購入時に10%の消費税を支払いすることとなるので、消費者の「痛税感」の緩和にはならないとの声がある。当初、検討してきた軽減税率は対象品目の税率を低く抑えるため、買い物の時点で支払う税額が少なくて済むという実感のあるものとなっていた。
マイナンバーカードは、本人の申請により交付されるものであり、すべての国民が手にするとは限らないため、カードの普及も課題のひとつである。又、全国のすべての小売店にまで情報端末を行き渡らせるには費用と時間を要する。そのため、小売店サイドでは端末の設置が遅れると、消費者は設置店の有無によって買い物店を選択し集客にも影響が出かねない。
平成29年4月の10%引上げ導入まであと僅かの期間しかなく、一定の周知期間を考慮すると今年末までには結論を出すことが求められる。マイナンバーカードの活用については、情報流出への懸念など多く問題点が指摘されており流動的な面が多い。今後の動向に注目したい。
カテゴリー:相談役 | trackback(0) | 2015年9月9日 11:18